この記事では、飲食の仕事がブラックすぎる理由と、対策方法についてお伝えします。
結論から言うと感じていらっしゃるとおり飲食は『ブラック』といってもいいです。
ただ、実は飲食業は他の業界と違って閉鎖的なので、ご自身の置かれた状況がブラックと気付かないという人も多いのも事実です。
今働いている環境がブラックで辛いという方は、この記事を読めば今の状況から脱することができますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
この記事を書いた人
 あんじ
あんじ
航空会社の客室乗務員として約15年勤務。CA時代には教官業務にも従事。退職後は、飲食店の集客コンサルタントをしながら、自らも飲食店で朝から深夜まで働くという激務の接客業に3年間携わってきました。
接客業をしてきたらこそ分かる、リアルな接客業に関するお役立ち情報をお伝えしていきます。
■資格:e-温泉マイスター/ソムリエ/国際利き酒師/TOEIC 930/秘書検定準1級
こんな飲食店はブラック確定!今働いている職場を見極める5つの特徴
飲食店の社員の仕事がきついけど、辞めるか続けるか悩んでいる方は、ご紹介する7つの基準を参考にしてみてください。
①:毎日サービス残業が当たり前、1日8時間勤務なんて関係ない
ブラック企業と呼ばれる理由の一つに、過酷な労働条件があります。
飲食店は営業時間が長く、休日や夜勤が多いため、従業員にとって負担が大きい場合があります。また、残業や休日出勤が当たり前で、適切な労働時間や休暇が取れない場合もあります。

私が勤務していた飲食店の1日の流れは(多分他のお店も一緒だと思いますが)
【調理場】
仕入れ → ランチ仕込み → 営業 → ディナー仕込み → 営業 → 片付け・注文
【ホール】
掃除 → 準備・ランチ営業 → 片付け・ランチ締め → 準備・ディナー営業 →片付け・締め作業
というスケジュールが、日々繰り返されています。
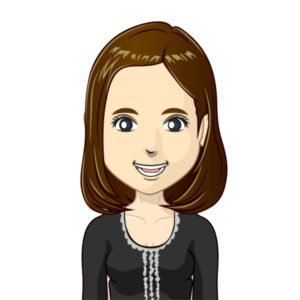
通常の業務の他にも、SNSでの発信だったり、予約サイトの管理や、シフト作成などの業務も発生します。
②:週6日以上の勤務が普通で、休みの日も会議や呼び出しがある
飲食店のほとんどは定休日がなく、年中無休で営業している店も少なくありません。
しかも人手不足なので、なかなか休むことが出来ないのも現状。
また、勉強会や会議がご自身の休みと重なってしまったら、最悪です。
休みだからといって欠席するわけにはいかないので、休日出勤が当たり前の環境になってしまいます。
③:労働時間に対して給料が低すぎる

出典:DODA
労働時間が長いのに、労働時間に見合ったお給料がいただけないのが飲食店社員の実態です。
DODAの2021年の業種分類別の平均年収によると、外食産業は、男女ともに最下位となっています。
給料が勤務時間に見合って高ければ、少しはモチベーションも上がりますよね。
でも実際、時給に換算して計算してみると、アルバイトの方が時給がよかったということも・・・・
④:全てが精神論で、会社全体が体育会系の会社
- 朝礼やミーティングがやたらと長い
- 精神論ばかりを押し付けられる
- パワハラ、暴力は当たり前
朝礼やミーティングでは、精神論や根拠のない感情や主観ばかりで、なかなか終わらない。
体調が悪ければ「気合が足りない」からと怒鳴られたり、根拠なく何でも精神論で進めようとする会社が多いのも飲食業界の特徴です。
というのも飲食業界は、1年中、朝から晩まで同じ空間で過ごし、同じ釜の飯を食うということもあり、他の業界と違って閉鎖的になってしまいます。
よく言えば家族みたいな存在ですが。。。
⑤:経費削減・売上ノルマがきつい
毎日のように、売上ノルマを課せられ、多店舗と競争させるような風潮。
売上を上げるには、SNSを使って宣伝したり、売上を上げるための施策を考えたり、社員の負担が増えます。
その一方経費削減を言われると、使いたい食材が使えなかったり、人件費がかかりすぎると怒られたり。
仕入れを削減するには料理の質も落ちるし、人件費を削減するためには、バイトに早くあがってもらうしかなく、結局は店舗の社員にしわ寄せがきくるという悪循環が起こってしまいます。
今の状況をそのまま我慢していると起こること
もし、職場が地獄と思いながらも我慢して働いていると、いろいろなことが起こってきます。
ストレスで取返しのつかないことをしてしまった同僚もいて、同じ思いをしてほしくないので真剣に、このままでいいのか自分と向き合ってください。
1.疲れているのに寝付けない、寝坊をする回数も多くなる
朝から夜遅くまで働いていて体は疲れているはずなのに、なかなか寝付けないということが起きてきます。
深夜に帰ってきたにも関わらず、ストレス解消でYouTubeや動画などを見てしまい夜更かししたり、最近は寝坊することが多くなることも。
そうなると仕事も集中力がなくなり、ミスが増えたり、遅刻が増えると社内で信頼がなくなってしまう可能性もあります。
2.お酒の量が増える
お酒で体をリラックスさせてストレスを解消しようとして、お酒の量が増える場合があります。
その状況が続くと、お店でもお酒を引っ掛けて、テンションを上げて仕事をするようになることも。
お酒を飲むとストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が増えます。飲む期間が長くなるにつれ、ストレス耐性が下がり、「抑うつ」の度合いも高まります。ストレスが溜まって、飲酒量が増えることは、「うつ病」に向かって、一気に突き進んでいることと同じです。
出典:週刊ダイヤモンド・オンライン
このままの状況を続けていると、アルコール依存症になり、仕事も人生もダメになってしまう可能性があります。
3.すぐイライラしてしまって、周りに暴言を吐いてしまう
毎日長時間で休みもなく働き続けると、冷静な判断が出来ない状況、客観的に物事を判断できなくなり、部下や、パートやバイトに暴言を吐いてしまうということも。
そんな状況になると、孤立してどんどん人が辞めていき、自分の首を絞めることになります。
ご自身で自覚できているうちに、一度職場を離れてみるのもありですが、退職して新しい道に進むのも強くおすすめします。
4.ストレス解消で大量に買い物&ギャンブルをしてしまう
ストレス解消で、買い物やギャンブルをするという人もいると思います。
もちろん少額であれば、誰でもやっていることで何らおかしくないのですが、気付いたらカードの請求額が大変なことになっている、カードローンをしてしまっている場合は、自分でストレスのコントロールが出来ない状況になっています。
実際、私の同僚は、ストレス解消で実際にお店のお金に手を出してしまいました。
取返しがつかない状況にならないためにも、すぐに飲食店の環境からは離れるべきです。
5.仕事が楽しくなくなる
お客さんに接していても楽しくない、むしろ「この客、むかつく」などの感情が出てしまっている場合は、今のあなたは接客業をしていてもやりがいを感じられなくなっている状態です。
この状況が続けば、お客さんからのクレームやグルメサイトへの書き込みがきたりして、ご自身の評価が下がるだけです。
最悪な場合、給料も下げられ休みをもらえなくなるということも起きます。
6.体に変化が出てくる
我慢して働き続けていると、ストレスで暴飲暴食が始まり太ってしまう、逆に食べても吐いてしまうということも起きる可能性があります。
また毎日ストレスばかりなので、常に表情が怖くなり、眉間にしわができる、口角が下がってしまう、目つきが悪くなるなど、ご自身の顔もストレスが刻まれていく可能性が高いです。
飲食業の業界の厳しさと人手不足が解消されないと状況は改善されないのが現実
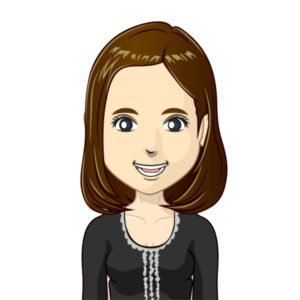
飲食業は、AIの力に頼れる部分もありますが、飲食業は人間ではないとできない仕事が多くあります。
しかも、テナントの家賃は高いのに、何百円といったコスパのいい料理を提供しないと競争に勝てないとか、仕入れも人参1本いくらといった計算をしないといけない業界です。
飲食業界の人手不足も短期のアルバイトは入っても、正社員は減っていくだけということも実際に起こっています。
今ブラックだと感じているなら、環境を変える準備をするのがおすすめ
- 今の職場がきついなら、無理して頑張る必要はない
- 今の仕事が全てではない
私が実際に経験してきて実感したのはこの2点です。
私も飲食店で働いてきて、朝から働いて帰るのはいつも深夜、体も家庭もボロボロになっていました。
40代という年齢のこともあり当時は辞める勇気がなかったのですが、今は退職できて別の業界の仕事をすることが出来ています。
自分から行動を起こしさえすれば、今の状況は変えられることができると実感しました。
まずはできることから行動を起こしてみましょう
「この先ブラック企業で働きたくない」、「自分にぴったりな仕事を見つけたい」という方は、出来ることからアクションを起こしていきましょう。
アクションを起こすことで、この先自分の希望と反するブラック企業で働くということがなくなるだけでなく、自己分析することでご自身に合った仕事を見つけることができるようになります。
①:ホワイト企業で働きたいと思ったらまずは転職エージェントに登録しましょう
今すぐ転職する、しないに関わらず転職エージェントにまずは登録して、一歩踏み出すことが大事です。
というのも、なかなか思うことがあっても忙しいからといって行動を起こす時間がないのが現実。
こういって自分の会社がブラックじゃないかと思った時こそ、今すぐ退職するしないに関わらず転職エージェントに登録して、広い世界を知ってみるのもおすすめです。
-

-
【2023年最新】飲食業の転職サイトおすすめ5選、飲食転職の経験の目線からご紹介
この記事では、飲食業の転職サイトのおすすめをご紹介します。
続きを見る
-
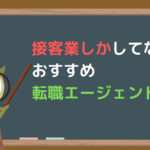
-
接客業しかしたことがない方に強いおすすめ転職エージェント7選
この記事では、未経験でも他業種に転職を成功させるためのおすすめ転職エージェントをご紹介します。
続きを見る
-
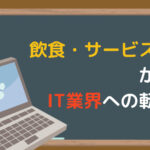
-
飲食やサービス業からITエンジニアに行きたい!経験がなくても転職しやすい職種と成功方法
この記事では、飲食業界からIT業界にチャレンジしたい人に向けて、実体験を通して成功する転職方法をご紹介します。
続きを見る
②:これまで経験してきたことの棚卸しをしてみる
- どんなときに仕事に充実感を感じていたか
- どんな成功体験があったか
- どんな失敗をしてきたか
- 辞めたいと思う時はどんな時か
- 自分が仕事に対して大事にしてきたこと
転職エージェントに登録するだけなく、これまでご自身が積み上げたキャリアの棚卸しをしましょう。
キャリアの棚卸しをすると、普段意識していない自分の思考パターンや、強み・弱みが明確になります。
③:客観的にこれからについてアドバイスをもらう
この先の仕事が楽しく、やりがいを感じられるといったことを実現させるには、あなたのことを長年見てきた家族や友人などから、ご自身の適性や性格を聞いてみるのもおすすめです。
客観的に見てくれることで、自分では普通だと思っていることが人より長けている部分であったり、実際には他人にしか見えない部分もたくさんあります。
もし、家族や友人に腹を割って相談しずらいという方は、一度無料のキャリアコーチングを利用してみるのもおすすめです。
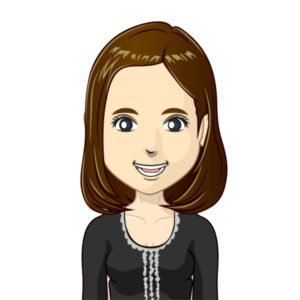
キャリアコーチングを受けることで
- 今の仕事がそもそも向いているのか
- あなたの強みを一緒に見つけてくれる
- どんな仕事が転職なのか見つけられる
- これから仕事や人生でやりたいこと、なりたい姿を見つけられる
キャリアコーチングはおためしで45分間の無料面談を体験することができます。
実際にキャリアコーチングの無料面談をした人の口コミ
最近インスタでよく見かけるポジウィル無料相談を試してみた!
45分たっぷり、無料お試しとは思えないクオリティだった仕事の悩み将来の悩み、もはや人生の悩みをプライベートも含めた観点で見てくれるし、アドバイスも的確でモヤが晴れた感じ☀️
ありがとうございました😊#ポジウィル無料相談感想— みー・×・🌗 (@mippi38_) June 4, 2021
仕事が満たされてもプライベートが満たされてなくては人生楽しくない、プライベートも仕事も楽しくなる未来を考えて行動しましょう。
5年後の自分が明るく過ごせるように選択しようと言ってくれて、45分が終わる頃には前向きに考え直そうと思えた。↓続く
— HOSHI (@hoshi0107p) April 23, 2021
無料面談でコーチの人と話すだけでも、いろんなことが整理されて、自分の進む道が分かるようになってきます
個人的には、キャリアのことや仕事のことで長い時間1人で悩み続けるのであれば、無料面談だけでも利用した方がいいです。
この記事のまとめ
飲食店の世界は、想像以上に過酷です。
飲食店がブラックと言われる理由
- 毎日サービス残業が当たり前、1日8時間勤務なんて関係ない
- 週6日以上の勤務が普通で、休みの日も会議や呼び出しがある
- 労働時間に対して給料が低すぎる
- 全てが精神論の飲食店の体育会系のノリに耐えられない
- 経費削減・売上ノルマがきつい
このいずれか1つでも当てはまるのであれば、あなたの体が壊れるだけなので、無理せず辞めてください。



